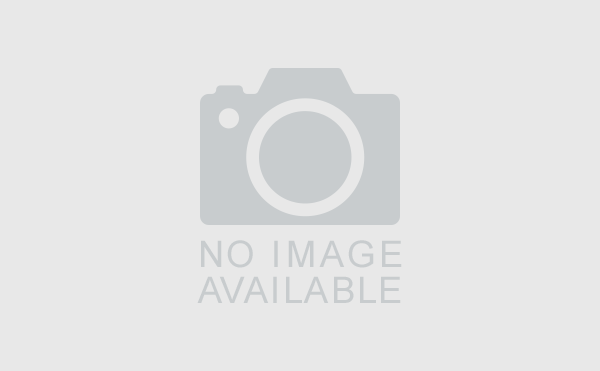健康経営で離職防止を!!
Ⅰ 背景
1 多くの中小企業では、人手不足対策として、「従業員の多能工化・兼任化」、「業務の一部外注化」、「残業の増加」に取り組んでいます。しかしながら 7割以上の中小企業は、依然として人手不足を感じている上に、そのうちの5割以上の中小企業は人手不足を深刻な問題と捉えています。
2 人手不足が深刻なのは、従業員が離職すると後任の人材がなかなか確保できないため、離職の連鎖が起こり売上げに大きく影響する事態になるからです。従って、 人手不足対策としては 従業員の離職防止を図ることが重要になってきます。
3 厚生労働省の調査によると 主な離職理由は、 ①「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」、② 「給料等の収入が少なかった」、➂ 「職場の人間関係が好ましくなかった」となっています。離職防止にとって重要なことは、これら3つの離職理由の原因が何かをつきとめ、その原因を改善することです。
Ⅱ 離職理由① 「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」の原因は 長時間労働です。
長時間労働は、従業員に様々な悪影響を与えます。労働負荷が増大することで、睡眠や休養が不足し心身の健康が悪化していきます。また、休暇を取ることができず家庭生活に支障が出ます。さらには、自由に余暇時間も取れずストレスが溜っていきます。このように長時間労働が原因で、従業員は「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」と感じ離職することになります。

Ⅲ 離職理由②の「給料等の収入が少なかった」の原因は 従業員の労働生産性低下です
健康関連の高リスク者と低リスク者との損失コストの差は、年間で30万円にもなります。このことは、健康関連の高リスク者が多くなると、損失コストが増加し労働生産性が下がるということです。その結果、企業の利益が上がらす従業員の給料等も上がりません。つまり、「給料等の収入が少なかった」の原因の一つとして、健康関連の高リスク者の増加に伴う労働生産性の低下が考えられます。

Ⅳ 離職理由➂の 「職場の人間関係が好ましくなかった」の原因は 職場のストレスです。
職場には様々なストレス要因があります。特に、ハラスメントやいじめといった人間関係からくるストレスは、離職の原因になります。

Ⅴ 健康経営は、以下の取組みによって、離職理由の原因となる「長時間労働・従業員の労働生産性低下・従業員のストレス」などを改善し、離職を防止していきます。
1 健康経営は 長時間労働対策によって長時間労働を改善し離職を防止します
2 健康経営は 生活習慣病対策によって従業員の労働生産性を向上させ離職を防止します
3 健康経営は メンタルヘルス対策によって従業員のストレスを改善し離職を防止します
健康経営の各施策は、従業員の心身の健康悪化を予防することを目的としているため、そこには予防医学の4段階の考え方が根底にあります。一次予防とは 病気の未然防止、二次予防とは 病気の早期発見・早期治療、三次予防とは 職場復帰支援、四次予防とは 治療と仕事の両立支援、です。
Ⅵ 健康経営による長時間労働対策
長時間労働は、最悪、過労死や自殺に繋がります。過労死は、長時間労働により睡眠不足が続くと血圧が上昇し、脳卒中や心筋梗塞を引き起こし死に至ることです。長時間労働により精神的負担が増大するとうつ病等の精神障害が発症し自殺に至ることもあります。長時間労働は被害者だけでなく、企業にも大きなリスクとなります。過労死や自殺に至った場合、遺族から裁判に訴えられその対応に追われるだけでなく、多額の損害賠償を請求されます。また、長時間労働による残業代の未払いがあると、労働基準監督署の臨検が行われその対応に追われます。長時間労働対策は待ったなしです。具体的対策は以下のとおりです。

Ⅶ 健康経営による生活習慣病対策
労働生産性の向上のためには健康関連高リスク者の減少が求められています。健康関連リスクのリスク要因は生活習慣病のリスク要因と同一であるため、生活習慣病対策に取り組むことが健康関連高リスク者を減らし労働生産性を向上させることができます。具体的対策は以下のとおりです。

Ⅷ 健康経営によるメンタルヘルス対策
職業性ストレスモデルによれば、人間関係の問題などの職場にある様々なストレス要因によって、ストレス反応が生じ、さらに進むとうつ病などの疾病が発症するとされています。うつ病が発症すると、精神科受診にためらいがちとなり治療も長期化します。又一旦治癒しても再発の可能性が残ります。従って、メンタルヘルス対策でうつ病の予防に取り組むことが重要です。同時にうつ病が治癒した後の支援制度を整えておくことも大切になります。具体的対策は以下のとおりです。

Ⅸ むすび
健康経営は、離職防止だけでなく追補資料4にあるように、従業員の健康意識の向上、コミュニケーションの活性化、企業イメージの向上など多くの効果が認められています。しかしながら、企業経営者が自らの健康と従業員の健康とを何よりも大切にするという強い理念を抱き、健康経営を行うのでなければこれらの効果は生まれません。企業経営者に強い理念がある限り、健康経営を通して企業全体にお互いの健康を気遣う思いやりのある企業文化が醸成されていきます。それが健康経営の一番の効果です。
追補資料